昔話に息づく日本の怪談「おいてけ堀」は、江戸時代の町に伝わる不気味な物語です。釣り人を襲う謎の声や、のっぺらぼうの出現といった怪奇現象は、今もなお私たちをぞくりとさせます。ここでは、この伝説の恐怖をお楽しみいただきます。
おいてけ堀
江戸の夜。月影は薄く、町外れの空に漂う雲が不吉な影を落としていた。ひっそりと流れる一本のお堀。その名は「おいてけ堀」。
この堀には奇妙な噂があった。釣り人が魚を手に帰ろうとすると、闇の奥から冷たい声が響くという――「おいてけ~」。その声に恐怖し、魚を捨てて逃げる者が後を絶たない。
「そんなモノ、怖くねぇ! ついでにそいつも釣ってやらぁ!」
町の魚屋、半兵衛が大口を叩いた。女房や仲間が止めるのも聞かず、彼はねじり鉢巻を締め、魚天秤を担ぎ、夜の堀へと向かった。
**
堀のほとりに着くと、空気がひやりと冷たかった。水面は月を映してゆらゆらと揺れ、不自然な静けさが辺りを支配していた。半兵衛は釣り糸を垂らし、しばし待つ。驚くほど簡単に魚が釣れる。
「ほれ見ろ、豊漁だ!」
だが、笑う彼の頬を突いたのは、湿り気を帯びた異様な風。ざわり、と背筋が粟立つ。辺りを見回すが、人影はない。ただ、柳の枝が重たげに揺れている。
「気のせいだ、バカバカしい」
キセルに火をつける。煙が渦を巻いて夜空に吸い込まれていく。と、どこからともなく囁きが聞こえた。
「……おいてけぇ……」
声が、堀の水面に染み出すように響く。半兵衛は耳を塞いだが、その声は頭の内に直接滴り落ちてくる。
「おいてけぇ……」
冷や汗が背を伝う。魚を抱え、逃げ出そうとした瞬間、水面が大きく揺れた。月の光が波に砕け、無数の白い顔が水底からじっとこちらを見つめていた。
「おいてけぇぇ……」
半兵衛は悲鳴を上げ、魚の天秤を投げ捨てて走り出した。
**
息を切らしてたどり着いたのは、柳の木の下。肩で息をしながら、辺りを見渡す。突然、背後から「カラン、コロン」と下駄の音。
振り返ると、白い着物をまとった女が立っていた。髪は夜の闇のように黒く、顔は血の気を失うほどに白い。女は微笑み、口を開いた。
「その魚、私に売ってくだしゃんすか」
「売らねぇ! みんなに見せるまでな!」
「そうですかい……なら、これでも?」
女が頬に触れる。指が滑るごとに、鼻、口、目が消えていく。のっぺらぼう。
半兵衛は喉がひゅっと鳴るのを感じ、恐怖に背を押されるように逃げた。
**
町外れのそば屋に駆け込み、主人にすがりついた。
「出たんだ! 顔が、顔がねぇ女が!」
主人は黙って頷き、ゆっくりと振り返る。その顔に、目も鼻も口もなかった。
「こんな顔でしたかい?」
声がひたり、と耳にまとわりつく。半兵衛は叫び声を上げ、転がるように店を飛び出した。
ようやく自宅へたどり着き、戸を叩いた。
「おい、開けてくれ! 女房! 開けてくれ!」
「どうしたえ? お前さん、真っ青だよ」
安心した。女房の声だ。中へ入ると、彼女が心配そうに覗き込んできた。
「出たんだよ、あれが、あの顔がない女が!」
「……そんなんじゃ、わかんねぇよ」
女房が頬を撫でた。顔が溶けるように消えていく。
「こんな顔じゃなかったかい?」
半兵衛はその場に崩れ、意識を手放した。
**
目が覚めると、冷たい地面の感触が背にあった。自宅の畳ではない。見上げると、揺れる柳の枝。その先には、月を呑み込むような真っ黒な水面が広がっていた。
「おいてけぇぇ……」
声が、耳元で、頭の中で、何度も響いていた。
その夜以降、半兵衛の姿を見た者はいない。
あとがき
江戸時代に伝わる昔話「おいてけ堀」と、のっぺらぼうの恐怖をご紹介しました。目に見えぬ怪異がもたらす恐怖は、時代を超えて私たちの想像をかき立てます。夜道を歩く際、背後に「おいてけ~」という声が聞こえてきたら、決して振り返らないでください――そこには、白い顔があなたを覗いているかもしれません。
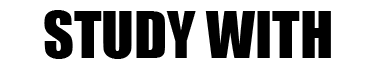

コメント