3. 健康と心の安らぎを願う言葉
書き初めでは、「心身の健やかさ」や「穏やかな一年」を願う語も人気です。
「無病息災」「安寧」「明鏡止水」「感謝」などの言葉は、静けさや調和を感じさせる筆文字になります。心を落ち着けて一筆ずつ書くことで、自分自身のリズムを取り戻すような書体が生まれます。
- 無病息災(むびょうそくさい)
病気や災いがなく健やかに過ごすこと。新年に最もよく書かれる言葉の一つ。 - 安寧(あんねい)
世の中や心が穏やかで安らかなこと。平和で落ち着いた印象を与える語。 - 平穏(へいおん)
波立つことなく静かで安らかな状態。日常の安定や心の平和を象徴する。 - 泰然自若(たいぜんじじゃく)
どんな出来事にも動じず、落ち着いているさま。内面の強さを感じさせる熟語。 - 明鏡止水(めいきょうしすい)
澄んだ鏡や静かな水のように、心が澄みきった状態。禅や書道に通じる静謐な語。 - 感謝(かんしゃ)
周囲への思いやりと感謝の気持ちを表す。人の心を温かくする普遍的な言葉。 - 和敬(わけい)
茶道の理念「和敬清寂」から。人を敬い、調和を大切にする心。 - 清風(せいふう)
清らかで涼しい風。比喩的に、さわやかな人柄や穏やかな気配を指す。 - 健やか(すこやか)
心身が健康であること。平易ながら、優しさと安定感をもつ言葉。 - 笑門来福(しょうもんらいふく)
笑いのある家には福が訪れるという意味。新年の書き初めにもよく使われる。 - 穏和(おんわ)
おだやかで人あたりのやさしいさま。静けさと柔らかさを感じさせる語。 - 安楽(あんらく)
心身ともに苦しみがなく、落ち着いている状態。古語から仏教用語まで幅広く使われる。 - 平安(へいあん)
心が安らかで穏やかであること。古来より平和の象徴として尊ばれてきた。 - 清心(せいしん)
欲や迷いを離れ、澄んだ心を保つこと。書道の精神にも通じる語。 - 和気(わき)
やわらかく、なごやかな雰囲気。古典文学にも多く登場する。 - 静寂(せいじゃく)
音もなく静まり返った状態。筆の止め・払いに美しさを感じさせる。
4. 人とのつながりを表す言葉
家族や友人、仲間との絆を大切にしたいときには、あたたかみのある語がよく選ばれます。
「家庭円満」「友愛」「信頼」「一期一会」などは、人との出会いやつながりの尊さを思い出させてくれる言葉です。リビングや玄関に飾っても、穏やかで心温まる印象を与えます。
- 家庭円満(かていえんまん)
家族の仲がよく、平和に暮らしていること。新年の願いごととして定番。 - 友愛(ゆうあい)
友人を思いやる優しい心。国際平和や友情を象徴する語でもある。 - 信頼(しんらい)
人や物事を強く信じ、頼ること。誠実な関係を築く基本となる言葉。 - 絆(きずな)
人と人との強い結びつき。家族や仲間への感謝を込める書として人気。 - 一期一会(いちごいちえ)
一生に一度の出会いを大切にするという茶道の精神。 - 和楽(わらく)
仲良く楽しく過ごすこと。古語として「和して楽しむ」とも表現される。 - 親和(しんわ)
互いに心が通じ、調和していること。関係が自然に安定している様子を表す。 - 良縁(りょうえん)
よい縁に恵まれること。恋愛・結婚だけでなく人間関係全般に使える語。 - 友誼(ゆうぎ)
友情や友人としての誠実な交わり。文語調の柔らかい響きをもつ。 - 調和(ちょうわ)
異なるものが無理なく溶け合うこと。人間関係にもよく使われる語。 - 信義(しんぎ)
誠実さと約束を守る心。友情や商取引など幅広い場面で重んじられる。 - 協力(きょうりょく)
力を合わせて一つの目的を果たすこと。行動の調和を示す。 - 扶助(ふじょ)
困っている人を助けること。思いやりと支援の精神を表す。 - 仁愛(じんあい)
思いやりと慈しみの心。儒教や論語にも登場する徳目の一つ。 - 共栄(きょうえい)
共に助け合いながら繁栄すること。社会や仲間意識に通じる語。 - 親睦(しんぼく)
親しく交わり、仲良くすること。団体活動などにも使われる穏やかな語。 - 和合(わごう)
人々が仲良く調和すること。仏教でも人間関係の理想として用いられる。
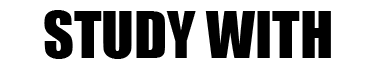

コメント