小論文は「序論→本論→結論」の3部構成で、限られた字数の中で自分の考えを論理的かつ説得力のある文章にまとめる技術が求められます。ここでは、800字の例題を用いながら、各パートの役割や文字配分の目安、書き方のポイントをご紹介します。
※注意: 本記事でご紹介する構成・文字配分はあくまで一例です。テーマや設問、字数・時間の制約に応じて、序論・本論・結論の配分や見出しの数は適宜調整してください。
1. 構成と文字配分の目安(800字の場合)
- 序論:80~120字(全体の10~15%)
- 本論:560~640字(全体の70~80%)
- 結論:80~120字(全体の10~15%)
この配分を意識することで、各パートに十分なスペースを確保し、読みやすいバランスを保てます。
2. 例題:「スマートフォン依存の是非について」
2.1 序論(約100字)
近年、スマートフォンは生活必需品となり、その利便性は計り知れない。一方で、長時間利用による依存が社会問題化しており、学業や対人関係への影響も指摘されている。本稿では、スマートフォン依存の問題点と対策を論じ、その是非を検討する。
ポイント:テーマ提起+立場表明。「本稿では…」で読み手に構成を予告。
2.2 本論(約600字)
問題点①:集中力の低下
授業中や会議中、通知音が鳴るとついスマホに手が伸び、注意がそちらに奪われることが少なくありません。ある実験では通知を確認すると集中回復に最低10分以上を要するとされ、実際に学生の約6割が授業中にSNSを閲覧して学習効率が著しく低下していると報告されています。さらに、長時間の画面注視はブルーライトによる眼精疲労や睡眠障害を招き、睡眠の質が低下すると翌日の業務や学習のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。しかし、通知オフ設定やアプリ制限機能、あるいはポモドーロ・テクニック用タイマーアプリを活用すれば、スマホを集中管理のための強力なツールとして利用することも可能です。
問題点②:対人コミュニケーションの希薄化
また、家庭や職場での「ながら会話」によって食事中や休憩中にスマホを操作し続けると、相手の表情や声色といった非言語情報を読み取る機会が減り、親子や同僚との感情的なつながりが希薄化するケースが報告されています。例えば、夕食時の会話時間が平均30%減少した家庭もあるといいます。一方で、SNSやビデオ通話を通じて遠方の家族や友人とリアルタイムに交流し、物理的距離を超えた絆を深める効果もあり、スマホが人間関係を強化する手段となる場合も見受けられます。
ポイント:理由は2つ程度に絞り、具体例やデータを添えて説得力を高める。
2.3 結論(約100字)
以上より、スマートフォン利用には利便性だけでなく依存リスクも伴う。依存防止には、利用時間の自己管理やアプリ制限機能の活用が有効である。適切な利用ルールを定め、テクノロジーと健全に共存していくことが求められる。
ポイント:序論で立てた主張を再確認し、具体的な対策や呼びかけで締めくくる。
3. 各パートの書き方ポイント
- 序論
- テーマ提起+立場の明示
- 構成予告(例:「本稿では…」)
- 本論
- 理由は2~3つに絞る
- 具体例(調査データ・実体験)で裏付け
- 接続詞(しかし・したがって)を適切に
- 結論
- 序論の立場を再確認
- 今後の展望や呼びかけをプラス
4. 書き終えたらチェックリスト
- 文字数:9割り程度(800文字なら720文字程度)書けているか
- 誤字脱字:確認
- 構成バランス:序論・本論・結論の配分を再確認
- 論理の飛躍:接続詞や段落のつながりをチェック
まとめ
800字程度の小論文も、配分と構成をおさえれば短時間で書き切れます。
- 序論:10~15%
- 本論:70~80%
- 結論:10~15%
まずは設問を正しく読み取り、メモと配分を意識して練習しましょう。論理的かつ具体的な文章で、説得力ある小論文を目指してください!
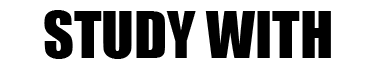

コメント