⑧ 和歌や文芸に関する言葉
歌や詩に使われる特有の言葉や、文学作品ならではの表現が登場します。
「ことば(和歌)」「ふみ(手紙・文章)」「ながむ(詠む)」など、和歌を詠んだり、物語を書いたりする文化に関連する語をまとめました。和歌の鑑賞や文学作品の理解に役立ちます。
1. うた(歌)
和歌、詩。五七五七七の形式が基本。
2. ことば(言葉)
和歌・文章・言葉づかいそのものを意味する。
※単なる「単語」以上の重みがある語。
3. ふみ(文)
手紙、文章、書物。
例文: ふみをしたためけり。=手紙を書いた。
4. ながむ(詠む)
詩歌を詠む。
※「物思いにふける」との混同に注意(同形異義語)。
5. よむ(詠む・読む)
和歌を作る、読む。
※「詠む」は和歌に特化、「読む」はもっと広い。
6. あそぶ(遊ぶ)
詩歌・音楽をたしなむ。
例文: 琴をあそびけり。=琴を奏でた。
7. たぐふ
(和歌や文章で)寄り添う、対応する。
※恋や連歌においても使われる。
8. にほふ
美しく照り映える、上品な美しさを持つ(和歌に頻出)。
※視覚的・感覚的な美の表現。
9. あはれがる
しみじみと感じ入る、感動する、同情する。
例文: 花の散るを見てあはれがりけり。
現代語訳: 花が散るのを見てしみじみと感じ入っていた。
10. こと(事・言)
出来事・言葉・内容。
※和歌の「題」としての「こと」も含まれる。
11. えん(艶)
風情・趣・美しさ・優雅さ。
※文学や恋愛表現の中で重視される。
12. えにし(縁)
人と人との宿命的なつながり、因縁。和歌においては「恋」「別れ」「再会」などで頻出。
例文: これは前世のえにしなりけり。
現代語訳: これは前世からの縁であったのだ。
13. あてやか
上品で美しい、気品がある(文芸的な理想像)
例文: あてやかなる詞の響き。
現代語訳: 上品で美しい言葉の響き。
14. ことのは(言の葉)
言葉・和歌の意。美しい表現として使われる。
例文: ことのはを尽くして語る。
15. ひま(隙)
心の隙間、感情の余白、文や詩の余情を意味することも。
※空間や時間だけでなく、和歌的情緒としても使われる。
⑨ 助動詞・助詞・文法的な語彙
「〜けり」「〜つ」「〜ぬ」「〜まし」など、文の形をつくる上で欠かせない語です。
古文では、助動詞の意味が文全体の意味を大きく左右します。ここでは入試頻出の助動詞を中心に、文法理解に不可欠な語を整理して紹介します。
1. けり
過去・詠嘆の助動詞。
例文: 花咲きけり。=花が咲いたのだった。
2. き
直接過去の助動詞。
例文: 昨日見き人ぞ。=昨日見た人だ。
3. つ
完了・強意の助動詞。
例文: 書きつ。=書いてしまった。
4. ぬ
完了・強意の助動詞。
例文: 行きぬ。=行ってしまった。
5. たり(完了)
動作の完了。「〜てしまった」「〜てある」。
例文: 書きたりけり。=書いてあった。
6. り
完了・存続の助動詞。
例文: 咲ける花あり。=咲いている花がある。
7. る(受身・尊敬・可能・自発)
四段活用の後につく。
例文: 見らる。=見られる(可能/受身など文脈で変化)。
8. らる
上二・下二・カ変・サ変の後に。
例文: 来らる。=来られる。
9. す
使役・尊敬の助動詞。
例文: 書かす。=書かせる。
10. さす
使役・尊敬。上二・下二・カ変・サ変に接続。
例文: 行かさす。=行かせる。
11. しむ
使役・尊敬。文語で格式高い文に出る。
例文: 読ましむ。=読ませる。
12. む(ん)
推量・意志・勧誘など。
例文: 行かむ。=行こう/行くつもりだ。
13. むず(んず)
「む」の強調形。
例文: 行かむずる。=行くつもりだ。
14. まし
反実仮想・ためらいの意志。
例文: 行かましかば。=行っただろうに。
15. まほし
希望の助動詞。「〜したい」。
例文: 見まほし。=見たい。
16. たし
希望。「〜したい」。
例文: 書きたし。=書きたい。
17. べし
推量・可能・当然・命令など多義的。
例文: 行くべし。=行くべきだ/行くだろう。
18. まじ
打消推量・不可能・禁止。
例文: 来まじ。=来るはずがない。
19. なり(推定)
音や声からの推定。「〜ようだ」。
例文: 雨の音なり。=雨の音のようだ。
20. なり(断定)
断定・存在。体言や連体形につく。
例文: 春なり。=春である。
21. たり(断定)
断定の助動詞。連体形接続。
例文: 人たり。=人である。
22. ごとし
比況・例示の助動詞。「〜のようだ」。
例文: 花のごとし。=花のようだ。
23. らむ(現在推量)
現在の原因推量。
例文: 何を思ふらむ。=何を思っているのだろう。
24. けむ(過去推量)
過去の原因推量・伝聞。
例文: なにを思ひけむ。=何を思ったのだろう。
25. し(助動詞「き」の連体形)
過去を表す「き」の変化形。
例文: 見し人。=見た人。
26. らし
推定の助動詞。「〜らしい」。
例文: 花咲くらし。=花が咲いているらしい。
27. めり
推定。「〜ようだ」。視覚的な推定によく使う。
例文: 春の夜の夢のごとくめり。=春の夜の夢のようである。
28. なりけり
「なり」+「けり」で断定と詠嘆が合わさった形。
例文: 春なりけり。=春であったのだなあ。
29. けらし
「けむ」+「らし」。過去の推定。
例文: 言ひけらし。=言ったらしい。
30. ざり(打消の連体形)
「ず」の連体形。「〜ない」。
例文: 行かざる人。=行かない人。
31. るる
受身・可能・自発・尊敬の助動詞「る」の連体形。
例文: 見るに見らるる心地す。
現代語訳: 見ると見られているような気がする。
32. ましけれ
「まし(反実仮想)」+「けり(詠嘆)」の複合表現。
例文: 行かましけれど…。
現代語訳: 行こうとは思ったのだが…。
33. らむず
「らむ」+「ず(打消)」の語で、「今ごろ~していないのだろう」の意。
例文: なにをか思はらむずる。
現代語訳: 何を思っていないのだろう。
34. ぬべし
「ぬ(完了)」+「べし(当然・推量)」の複合表現。
例文: 花は咲きぬべし。
現代語訳: 花はきっと咲いているはずだ。
35. つつ
意味: 動作の並行(〜しながら)、継続(〜し続けて)などを表す接続助詞。
例文: 花を見つつ、物思ひにけり。
現代語訳: 花を見ながら、物思いにふけった。
36. ながら(接続助詞)
〜のままで、〜けれども。
例文: 子ながら賢し。
現代語訳: 子どもでありながら賢い。
37. ども(接続助詞)
逆接(〜けれども)。
例文: 知れども言はず。
現代語訳: 知っているが言わない。
38. にしがな
品詞・意味: 終助詞。自己の願望をやわらかく表す。「〜したいなあ」※和歌や物語に出る控えめな願望表現
例文: 君に逢はばやにしがな。
現代語訳: あなたに逢いたいなあ。
39. 〜ばや
自己の願望(〜したい)。
例文: 行かばや。
現代語訳: 行きたいものだ。
⑩ その他よく使われる語(副詞・接続語など)
「さて」「なほ」「かく」「よに(決して)」など、意味のつなぎや強調に使われる語です。
場面を切り替えたり、感情を強調したり、話の流れを整理するための副詞・接続詞・感動詞などの頻出語を扱います。見落としやすいですが、正確な読解に欠かせない存在です。
1. なほ
やはり、それでもなお。
例文: なほ、昔の方がよし。=やはり昔のほうがよい。
2. やがて
そのまま、すぐに。
例文: やがて帰りぬ。=そのまま帰った。
3. さて
そうして、そのまま。
例文: さて、御文を読まれけり。=そうしてお手紙を読んだ。
4. かく
このように。
例文: かく言ふ人もありけり。=このように言う人もいた。
5. しか
そのように。
例文: しか言ふはあやし。=そのように言うのはおかしい。
6. とかく
あれこれと、いろいろと。
例文: とかく言ふまじ。=あれこれ言うまい。
7. いかが
どのように、どうして(反語表現によく使われる)。
例文: いかがあらん。=どうであろうか/どうしてそうであろうか(反語)。
8. あまた
たくさん。
例文: あまたの人の中に。=多くの人の中に。
9. つねに(常に)
いつも。
例文: つねに参りけり。=いつも参っていた。
10. ただちに(直ちに)
すぐに、そのまま。
※「ただに(ただ)」と混同注意。
例文: ただちに御前を出でぬ。=すぐに御前を出た。
11. いかに
どうして、どのように。
例文: いかにせむ。=どうしようか。
12. いかで
どうして、なんとかして(願望とともに使う)。
例文: いかで都に帰らむ。=なんとかして都に帰りたい。
13. げに
なるほど、本当に。
例文: げに、その通りなり。=なるほど、その通りだ。
14. よに(世に)
実に、決して〜ない(否定を伴って)。
例文: よに許さず。=決して許さない。
15. なにしおはば
意味:どれほどの価値があろうか(反語表現)
例文: 名にしおはば、いざ言問はむ。
現代語訳: 名前があるなら、さあ尋ねようではないか。
古文単語が分かれば、古文が楽しくなる
古文が苦手な人の多くは、「文章が読めない」のではなく「単語が分からない」のです。
この300語をマスターすることで、どんな古文も見慣れた言葉の集合体に変わります。
毎日のちょっとした学びが、将来の進路、教育費の節約、そして学力向上につながります。
家庭学習でも、古文参考書の補助資料として活用してください。
少しずつで構いません。今日から、「古文単語」の学習を進めていきましょう。
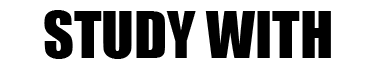

コメント