10. 環境への配慮
地球温暖化やごみ問題など、私たちの生活と地球環境は深く関わっています。このカテゴリでは、「自分にできることは何だろう」と考えるきっかけになるような、身近なエピソードや行動のヒントを伝えます。
1. みんなの小さなエコが集まると…
ぼくたちが毎日できる小さなエコは、実は地球を変える大きな力になります。例えば、牛乳パックやペットボトルをきれいに洗って正しく分別すること。学校帰りに道ばたのゴミを拾うこと。部屋を出るときに電気をこまめに消すこと。一人ひとりの行動は小さくても、クラス全員が同じ気持ちで取り組めば、資源のムダ遣いを減らし、CO₂排出量を抑えられます。先日、わたしのクラスでペットボトル回収をしたら、わずか一週間で十五キログラム集まり、リサイクル工場に届けることができました。これはたった十五人の仲間が協力した結果です。もし全校生徒が同じように続けたら、もっと大きな成果になるでしょう。今日から、自分にできるエコを見つけ、友だちと声をかけ合って実践してみませんか?小さな一歩が未来の地球を笑顔にします。
2. エコ習慣
私たちの毎日は、小さな選択と行動の繰り返しでできています。エコは難しく考えなくても、日常の習慣に取り入れられるものがたくさんあります。例えば、歯磨きのときに水を出しっぱなしにせず、コップに水をためて使う。部屋を出るときには、テレビや照明のスイッチだけでなくコンセントも抜く習慣を。お弁当では、使い捨て容器の代わりにマイ弁当箱やエコラップを使ってごみを減らす。地球と自分を大切にする習慣を今日から始めましょう。これらの習慣を続けることで、学校全体のゴミ量や電気使用量の削減につながります。実際、先輩たちのマイボトル運動では、去年一年でプラスチックゴミを二割以上減らした例もあります。自分一人の行動は小さくても、クラスのみんなが同じ目標を持てば大きな成果になります。まずは今日から、あなたが無理なく続けられるエコ習慣を一つ選んで始めてみましょう。仲間とアイデアをシェアして、楽しく競い合いながら続けると、より効果的です。小さな日々の工夫が、未来の地球への大きな贈り物になります。
3. ゴミ分別で地球を笑顔に
皆さん、ゴミ分別はただの面倒な作業ではありません。一つひとつの空き缶や紙くずを正しく分けることで、資源が新しい製品に生まれ変わり、地球の負担を減らすことができます。たとえば、プラスチックとペットボトル、燃えるゴミと燃えないゴミを分別するだけで、廃棄物のリサイクル率が大幅にアップします。実際に、わたしのクラスでは一ヶ月でリサイクルゴミが五キログラムも増え、リサイクル工場へ送る量が増加しました。そして、廊下に貼った分別シールを見ながら友だち同士で分別をチェックするゲーム感覚の取り組みも大好評です。今日から、教室や自宅でゴミを出すときに「これはどこ?」と意識して分別し、友だちと一緒に楽しく続けてみましょう。さらに、家族と協力してリサイクルボックスを作るのもおすすめです。一人ひとりの協力が未来の環境を守る大きな力になります。地球を笑顔にする分別、今日からはじめましょう。
4. ライトオフタイムで地球に休息を
みなさん、夜になっても部屋の明かりをつけっぱなしにしていませんか?照明は便利ですが、消費する電気は地球からの貴重なエネルギーでもあります。そこで提案したいのが「ライトオフタイム」です。毎日決まった時間、たとえば夜九時から十五分間、全ての電気を消して静かな時間を持ちましょう。この時間に読書をしたり、家族と話したり、星空を眺めたりすることで、いつもと違う発見が生まれます。わたしの家でも、一週間試しただけで電気代が五パーセント減り、月末の請求書で家族みんなが驚きました。学校では「ライトオフタイムチャレンジ」を行い、グラフで達成率を競うと盛り上がりました。消灯中は懐中電灯を使って防災意識も高めてみましょう。家族や友だちと感想を分かち合って、楽しく続けましょう。地球に休息をプレゼントするこの時間を、みんなで広げていきましょう。
5. 一滴の水が支える私たちの未来
みなさん、私たちが毎日何気なく使っている水は、遠くから長い旅を経て私たちのもとに届いています。歯磨きや手洗いで出しっぱなしにした水、長いシャワータイム――そんな一滴一滴を大切にすることが、未来の地球を守る大きな一歩です。実際、歯磨きのときにコップを使うだけで一回あたりの水量を約5分の1に減らせますし、シャワーを1分短くするだけで年間約100リットルの節水になります。学校の屋上に置いた雨水タンクを一週間使ったクラスでは、運動場の雑草取りにその水を活用し、大活躍しました。家庭でも家族と一緒に「節水チャレンジ」をして、毎日の水使用量をグラフに記録すると楽しく続けられます。小さな気づきと工夫が集まれば、やがて大きな力となり、私たちの未来を輝かせるでしょう。
6. 今日から始めるエコライフ
みなさん、エコは特別なことではありません。毎日の習慣を少し変えるだけで、地球にやさしい生活が始まります。例えば、マイボトルを持ち歩いて使い捨てプラスチックを減らす。学校の行き帰りに車ではなく自転車や徒歩を選び、CO₂排出量を減らす。家では使っていない電子機器のコンセントを抜き、シャワーを1分短くする…こうした小さな行動を3つ決め、1週間続けてみましょう。わたしのクラスでは「エコライフ宣言カード」を作り、宣言した人同士で毎日の達成度を報告し合い、楽しく競い合うことで続けやすくなりました。今日から始めるエコライフで、自分も周りもハッピーにしていきましょう!
7. 今日の小さな節約
みなさん、毎日の暮らしで気づかないうちに使っている電気や水。今日はその「小さな節約」を紹介します。まず、部屋を出るときは照明やテレビのスイッチだけでなく、待機電力を減らすためにコンセントも抜きましょう。一ヶ月続けると電気使用量が約10%減ることもあります。次に、歯磨きや手洗いのとき、水を出しっぱなしにせず、コップにためて使うと、一回あたり5〜10リットルの節水が可能です。さらに、お弁当では使い捨てのラップやカップの代わりにマイ弁当箱を使い、ごみを減らしましょう。これらの小さな節約を家族や友だちとゲーム感覚で記録し合うと、楽しく続けられます。実際、友だちと節約記録を1ヶ月競い合った結果、わたしたちのクラスは電気使用量を12%、水使用量を8%削減でき、学校新聞にも取り上げられました。あなたも今日から始めて、みんなに広めてみませんか?
8. 地球のためにできる3つのこと
みなさん、地球を守るために私たちにできることは身近にあります。まず一つ目は「ゴミの分別」です。紙やプラスチック、缶、ビンを正しく分けることで資源を再利用でき、廃棄物を減らせます。わたしのクラスでは分別用のステッカーを貼ったゴミ箱を用意し、毎週チェックして学級委員がランキングと点数を発表する取り組みを行い、リサイクル率が20%向上しました。二つ目は「節電」です。使っていない照明やテレビの電源を切ることはもちろん、冷蔵庫の開閉を短くする、パソコンの省エネモードを活用するなど、小さな工夫で一日あたり数ワットの節電ができます。三つ目は「節水」です。歯磨きや手洗いの際にコップを使う、シャワーを1分短くするなどで、一回あたり5〜7リットルの節水効果があります。これら三つの行動を毎日の習慣にすることで、学校全体や家庭のエネルギー・水資源を大きく節約できます。まずは今朝から、一つずつ実践してみましょう。仲間を誘って楽しく続ければ、もっと大きな変化を生み出せます!
9. 水の大切さ、一緒に考えよう
みなさん、私たちは1日におよそ200リットルもの水を使っていると言われています。歯磨きで出しっぱなしにした水、洗顔やシャワーのちょっとしたムダが積み重なると、大きな量になりますよね。そこでおすすめなのが、「水ダイアリー」。毎日使った水の量を記録し、ムダを見える化することで節水ポイントがわかります。例えば、歯磨き中はコップを使うだけで一回あたり約5リットル、シャワーを1分短くするだけで年間約1000リットルの節水に。学校のプランターに使った雨水を貯める仕組みを作ったクラスでは、夏休みの水やり費用を半分以下に減らせたそうです。まず今日は、洗い物をため洗いにチャレンジしてみましょう。小さな工夫が未来の水資源を守る大きな一歩になります。
10. 電気を消して未来を照らそう
みなさん、照明やテレビの消し忘れで、知らないうちに多くの電気を無駄遣いしていませんか?家庭や学校で使う電力は、発電時に二酸化炭素を排出することが多く、地球温暖化の原因にもつながります。そこで「消し忘れゼロ大作戦」を提案します。教室や自室のスイッチ回りに「消した?チェックシール」を貼り、帰る前に友だちとお互いに確認し合うだけで、電気使用量が約10%減ることもあります。また、LEDランプや省エネモード搭載の機器に変えると、さらに節電効果が高まります。夜は家族で「消灯タイム」を設け、懐中電灯で星を観察したり、ろうそくの灯りでボードゲームを楽しんでみてください。暗闇の中で得られる新しい発見が、電気を消すことの楽しさと大切さを教えてくれます。未来を明るく照らすのは、むやみに電気を使うことではなく、賢く節電するあなたの行動です。
ポイント
- 例文の役割を理解する
- 挨拶や礼儀のテーマに沿った一分間の流れ(導入→具体例→まとめ)をつかんでください。
- 使われている「おはよう」「ありがとう」などのキーワードや、相手への問いかけ、締めの呼びかけの構成を応用しましょう。
- 自分の経験を盛り込む
- 実際に学校や部活、家庭で感じた出来事を具体的に挙げると、聞き手の共感を得やすくなります。
- たとえば、友達に助けられたエピソードや、自分が挨拶を変えてみて感じた変化など、自分ならではの体験を書き入れましょう。
- オリジナリティを大切に
- 例文をそのまま使うのではなく、言い回しや順序を変えて、自分らしい語り口でまとめます。
- ポイントは「聞く人に伝わるか」「自分の思いがこもっているか」です。
- 一分間に収める練習
- 書いた原稿は声に出して読み、時間を計ってみましょう。
- 検討が必要な箇所は短く削るか、言葉をシンプルにすることで、聞きやすいスピーチに仕上がります。
「伝える力」を育てよう
スピーチは、うまく話すことよりも、「自分の言葉で伝えようとすること」がいちばん大切です。
今回紹介した100本の例文は、みなさんが「ちょっと話してみようかな」と思えるように作られています。最初は例文を読むだけでもOK。少しずつ、自分の気持ちを重ねていけばいいんです。
言葉には、人の心を動かす力があります。
それは、大人だけじゃなく、中学生のあなたにもちゃんとある力です。
「自分の考えを伝えられるって、気持ちいい!」──そう思える日が、きっとすぐに来ます。
今日のスピーチが、あなたの新しい一歩になりますように。
✅ FAQセクション(見出し+本文)
❓中学生のスピーチはどれくらいの長さが適切ですか?
中学生のスピーチは、1〜2分程度が聞き手の集中力を考えても適切です。文字数でいうと約400〜500文字が目安になります。短くても内容が伝われば十分です。
❓朝礼で使えるスピーチのテーマは何がありますか?
努力、友情、夢、マナー、挑戦、環境問題などがおすすめです。日常生活と結びつけると、聞いている人の共感を得やすくなります。
❓緊張せずにスピーチをするコツはありますか?
何度か声に出して練習することで、自然に話せるようになります。また、話す相手を「友達の一人」だと思って伝えると、緊張が和らぎます。
❓中学生本人がスピーチを書くときのポイントは?
「自分の体験」や「感じたこと」を入れると、オリジナリティが出て伝わりやすくなります。最初に結論を話すと、話がぶれずにまとまりやすくなります。
❓先生が生徒に読ませるためのスピーチ例もありますか?
はい、本記事では「学ぶことの楽しさ」「礼儀」「挑戦」など教育的価値のあるスピーチ例をカテゴリ別にご用意しています。教材としてもご活用いただけます。
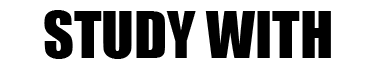

コメント