夏休みの宿題や自由研究で「俳句を作りなさい」と言われたものの、どんな言葉を選んでどう作ればいいのか、悩んでいませんか?
特に小学生の場合、「季語ってなに?」「俳句ってむずかしい?」という不安を抱えることも多いでしょう。
ここでは、小学生にもやさしく理解できる「夏の俳句」と「季語や意味」を37句にわたって紹介します。季語にはどんな種類があるのか、それぞれどんな風景や気持ちを表すのかをわかりやすくまとめました。
夏の空、セミの声、すいかの味、夜のお祭り…。子どもたちの目線から切り取った季節の情景は、大人の心にもどこか懐かしさを感じさせるものです。
この記事を読めば、小学生でも「俳句って楽しい!」と感じられるはずです。
俳句の宿題や作文の参考に、今すぐご活用ください。
小学生向け夏の俳句例 一覧
夏の風物詩としての季語とは?小学生にもわかる意味と使い方
俳句における「季語」とは、季節の情景や空気感を一言で表す言葉のことです。特に夏の俳句では、「すいか」「あさがお」「せみ」「夕立」など、身近な体験や自然の変化を表す季語が多く使われます。小学生でも理解しやすい夏の季語には、学校や家庭、地域の夏祭りなどで見かけるものが多いため、日常の中から自然に取り入れることができます。俳句で季語を上手に使うことで、読む人に「その季節らしさ」が伝わるようになり、作品に奥行きが生まれます。
1. 小学生でも使いやすい!夏の自然を表す季語の例とその意味
夏の俳句を作るときによく使われる自然に関する季語には、「入道雲」「青空」「夕立」「川遊び」「風鈴」などがあります。これらの季語は、自然の様子や気候の特徴をとてもわかりやすく伝えてくれます。たとえば「入道雲」は、空にわき上がる大きな雲で、夏の暑さや午後の雷雨を連想させる情景を表します。こうした季語は、観察力を育てるとともに、身の回りの風景に興味を持つきっかけにもなります。夏ならではの自然を描いた俳句は、感性豊かな作品に仕上がりやすいです。
①夏の川(なつのかわ)
なつのかわ みずにうつった あおいそら
季語:「夏の川」は、水遊びや涼を感じる場所として親しまれる風景。清涼感のある季語です。
説明:
水面に映る空を通して、川の涼しさと夏の空の青さをいっしょに描いています。
②ひまわり
ひまわりが ぼくのえがおと にているね
季語:「ひまわり」は夏を代表する花で、太陽の方を向いて咲くことから元気の象徴とされています。
説明:
ひまわりの明るい姿と自分の笑顔を重ねることで、花に親しみを持つ気持ちを表現しています。
③朝顔(あさがお)
あさがおと いっしょにおきる なつのあさ
季語:「朝顔」は夏の朝に咲く花で、昔から観察日記などでも親しまれてきた定番の夏の植物です。
説明:
毎朝決まって咲く花と、自分の朝の始まりが重なることで、夏の生活リズムを表しています。
④夏草(なつくさ)
なつくさに くつのあとだけ のこってる
季語:「夏草」は夏の強い日差しの中でも勢いよく伸びる草のこと。生命力の象徴でもあります。
説明:
夏草の中に残る足あとから、さっきまで遊んでいた友だちの存在を感じさせる情景です。
⑤夕焼け
ゆうやけに つれてかえった かたつむり
季語:「夕焼け」は夏の終わりを感じさせる風景のひとつで、赤く染まった空が印象的です。
説明:
夕焼けの空を背景に、小さな発見(かたつむり)を大切に持ち帰る、子どもらしい優しさを描いています。
⑥夏の海(なつのうみ)
なつのうみ うみにもぼくの こえがとぶ
季語:「夏の海」は、泳ぎに行ったり貝をひろったりする場所として、夏休みの定番の風景です。
説明:
広い海に向かって叫ぶ楽しさや解放感を、そのまま俳句にしています。
⑦風(夏の風)
なつかぜに シャツがふくらむ ふねみたい
季語:「夏風(なつかぜ)」は、暑い季節にふく風のことで、涼しさや一瞬の心地よさを伝えます。
説明:
風でふくらんだシャツを船にたとえることで、想像力あふれる子どもの視点が表れています。
⑧夏の山
なつのやま おおきくいきを すいこんだ
季語:「夏の山」は、新緑が生い茂り、昆虫や鳥の声が響く生命力豊かな場所として描かれます。
説明:
大きな自然を前にして、思いきり深呼吸したくなる気持ちを素直に表現しています。
⑨夏空(なつぞら)
なつぞらに とんでけぼくの おもいごと
季語:「夏空」は、青く広がる晴れた空を表す季語で、心を開放するようなイメージがあります。
説明:
自分の気持ちや夢を空に向かって投げるような、自由で前向きな気持ちを詠んでいます。
⑩草いきれ
くさいきれ ねころぶぼくの うであつい
季語:「草いきれ」とは、夏の草むらから立ちのぼる、むんとした熱気のこと。独特の暑さを感じさせる言葉です。
説明:
草むらで遊んだあとに、地面の熱やにおいを肌で感じる、リアルな夏の体験を描いています。
⑪木陰(こかげ)
こかげには なつのひみつが かくれてる
季語:「木陰」は夏の強い日差しをさえぎる、木の下の涼しい場所のこと。休憩や遊び場として親しまれます。
説明:
木陰の中に秘密基地のような感覚を感じる、子どもらしい想像力を表しています。
⑫蝉(せみ)
せみがなき じっときいてる ぼくのなつ
季語:「蝉」は夏の代表的な昆虫で、鳴き声が季節の訪れを知らせます。
説明:
うるさいはずのセミの声に耳を澄ます静けさが、逆に「夏の音」を際立たせています。
⑬ホタル
ほたるのひ そっとひかって またくらい
季語:「ホタル」は初夏から夏にかけて見られる発光する昆虫で、幻想的な夜の情景を演出します。
説明:
光っては消えるホタルの様子を静かに観察する、やさしい眼差しの俳句です。
2. 食べものの季語を使った夏の俳句の魅力とは?子どもにも伝わる味覚の情景
夏の食べものは、俳句の題材としても大人気です。すいか、ところてん、かき氷、そうめんなど、暑い日に食べたくなるものはすべて季語として使えます。これらの食べものを俳句に取り入れると、味覚だけでなく、冷たさや楽しい時間までもが自然に伝わります。特に小学生が自分の好きな夏の食べ物を使って俳句を詠むと、その子ならではの個性が作品に表れ、楽しく学ぶことができます。身近な食体験と俳句を結びつけることが、創作の第一歩になるのです。
①かき氷
かきごおり あおいべろだと わらわれた
季語:「かき氷」は夏祭りや屋台で人気の冷たいデザート。見た目の鮮やかさも印象的です。
説明:
かき氷を食べて舌が青く染まった様子を、笑い合う光景として描いています。
②ところてん
ところてん つるっとのどを ぬけていく
季語:「ところてん」は昔ながらの夏の冷たい和菓子。酢や黒みつで食べることが多いです。
説明:
つるつると口の中からのどをすべるように入っていく様子を、そのまま表現しました。
③そうめん
そうめんを ながすながれに こえをのせ
季語:「そうめん」は夏の定番料理。冷たくゆでた麺を水に流しながら食べる「流しそうめん」も人気。
説明:
そうめんと一緒に自分の声も水に流れていくような、遊び心を詠んでいます。
④あんみつ
あんみつの みずのうえにも なつひかり
季語:「あんみつ」は寒天・あんこ・果物などを組み合わせた涼しい甘味です。
説明:
寒天のつるんとした表面に、夏の光がきらきら反射している様子を描いています。
⑤ラムネ
らむねあけ ビーだまゆれる ぼくのなつ
季語:「ラムネ」はビー玉の入った炭酸飲料で、夏祭りや縁日などの風物詩。
説明:
ラムネ瓶の中で揺れるビー玉を「ぼくの夏」と重ね、懐かしさと清涼感を伝えます。
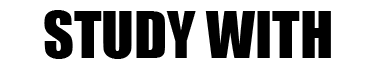

コメント